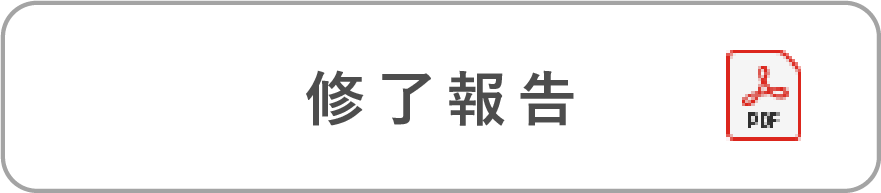奨学生インタビュー
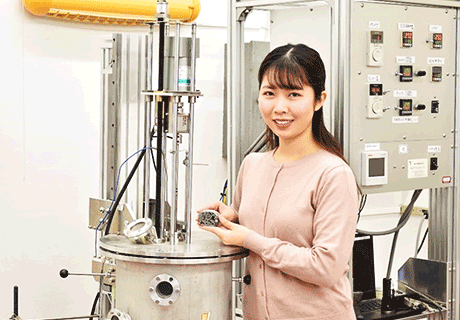
髙松 聖美さん
早稲田大学大学院
基幹理工学研究科
材料科学専攻
鈴木研究室
高校生の時から発泡アルミニウム合金の見た目の面白さ、利用可能範囲の広さに惹かれ、今の研究室を選びました。修士1年次に参加した国際学会にて、論文執筆を勧められ博士進学を決意。材料科学専攻の1期生として進学し、材料プロセス工学に基づいた研究を行っています。
奨学生応募の動機は?
本奨学生制度へ応募したきっかけは、指導教員である鈴木進補先生の紹介でした。修士1年の夏に参加した国際学会で発泡金属界の権威である教授から論文を期待され、すでに博士進学を決意した頃だったと覚えています。率直に言えば、応募を決めた一番の理由は4年に渡る研究費および学費補助に魅力を感じたからでした。しかし結果として奨学生への応募は自らの将来像を見つめる良い機会となったと思っています。発泡金属を研究することは、金属の溶解、鋳造・凝固だけでなく、ミクロ組織の観察、複雑形状などビッグデータの解析など、幅広く金属を研究することと同義です。そのためこの研究を通じて、材料プロセスの新たな創造に繋がる重要な知見を得たいと考えています。
将来はアルミニウム合金を始めとする材料プロセスを研究する女性研究者として、これからの時代の先陣を切る存在になりたいと考えています。近年は理系へ進学する女子学生も多いと聞きますが、そのロールモデルとなるような研究者になることで次世代へと貢献していきたいです。
研究内容を教えてください。
発泡アルミニウム合金は内部に多数の気孔を持つ、スポンジに似た見た目の金属部材です。高い衝撃吸収性、吸音、吸熱といった特性から、エネルギーマテリアルとしての利用が期待されています。
発泡Al合金は、熱分解でガスを発生する発泡剤をAl溶湯に添加し、発泡した状態で急冷凝固することで作製されます。この時、溶湯の粘度が低いと発泡途中で気孔同士が繋がり、十分な特性を得ることができません。そこで本研究では、初晶粒子の晶出によって見かけ粘度を増大させたセミソリッドスラリーを発泡させる、セミソリッド発泡法に着目して研究を行っています。セミソリッド発泡法で作製された発泡Al合金は従来法で作製された物と比べて、より長時間気孔形状を保持可能です。そのメカニズムとして、初晶粒子が気孔間で詰まる"せき止め効果"が存在しますが、効果発現に最低限必要な初晶粒子量は未だ不明です。本研究は、浸透理論等を用いることで、その具体的な量および詳細条件を明らかにすることを目的としています。
軽金属奨学会 特別奨学生卒業にあたり
修士2年からの4年にわたる長い間、ご支援いただきました奨学会の皆様に感謝申し上げます。無事に博士号を取得し、公私ともに充実した学生生活を送ることができましたのも、特別奨学生制度のおかげです。
世の中には数多くの博士学生向け助成金制度がありますが、修士2年から学費支援と研究費支援をいただける制度は類を見ず、またその金額もトップレベルであり、非常に恵まれた環境であったと思います。さらに軽金属学会では特別奨学生セッションを設けていただき、分野を超えて多くの研究者の皆様と議論することができました。特に、奨学生のメンバーはそれぞれまったく違うことを研究テーマにしているにも関わらず、学会毎に研究の話で盛り上がり、私はいつも彼らの研究成果のすばらしさに身が引き締まる思いでした。将来、軽金属を担うことを志す私としては、このような手厚いご支援のもとで研究できたことが本当にありがたく、これからの研究生活も頑張っていきたいと思います。
軽金属を専攻しこれから進学を考えている皆様は、ぜひ本制度に応募し、ステップアップしてください。同世代の博士学生と切磋琢磨しながら、充実した研究生活を送ることができる良い機会になると思います。
改めて、これまでのご指導、ご支援に深く感謝申します。